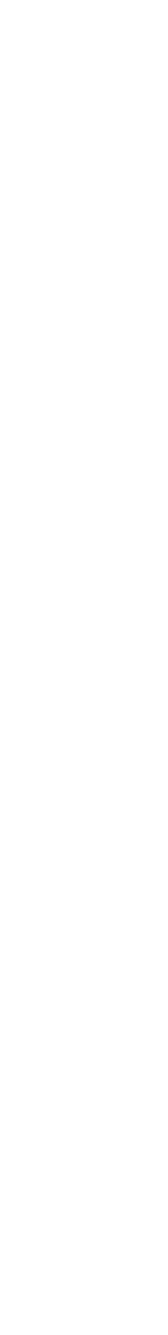-
one emerging possibility気持ちのいい午後だった。日差しは柔らかく、空は澄んでいる。
ゆるやかな丘の草花を撫でて通り抜ける風は涼しく、いつまでもこうしていられそうだ。
丘の斜面に腰を下ろしていた『彼』は、立てた膝に両腕をもたれさせて、もう三十分以上ぼうっと景色を眺めていた。
眼下には小さな街並みが広がっている。
白い壁に青や緑の屋根、家々の間を抜ける曲がりくねった石畳。
中央には大きな建物があって、その側に寄り添う尖塔から真白い大きな鳥が一羽飛び立つのが見えた。 -
「……のどかだなぁ」
誰に向けるでもなく、ぼんやりと呟く。
ここから見える景色に変わりはない。
この島にやってきてから七年、ずっと同じ景色を、同じ温度の中で見ている。
きっとこの先も、同じ景色を見るのだろう。目元まで延びた緑色の長い前髪ごしに、ここ『イシャナ島』の景色を。
ふと、声が聞こえて、彼は力の抜けきっていた背筋を伸ばした。
声は自分の名前を呼んでいるようだ。となれば、声の主にあたりはつく。こんななにもない場所にまで、自分を探しに来てくれるような人はひとりしか知らない。 -
「カズマさぁ~ん」
のんびりと間延びした、緊張感に欠ける声が、丘の下から彼を呼ぶ。
やっぱりだ。
彼は――カズマ=クヴァルは、芝生の坂道を小走りに上ってくる姿に、わずかに口元を緩めた。
やってきたのはひとりの少女だ。
たっぷりとしたフード付きの黄色いマントを羽織って、大きな丸眼鏡をかけている。
フードからは柔らかなプラチナブロンドの髪がこぼれていて、その優しい色が彼女の新緑色の瞳によく似合っていた。 -
「ふふ、カズマさん、この時間はよくこちらにいらっしゃいますから。大正解でしたぁ~」
服をはたきながら立ち上がったカズマを見上げて、黄色いフードの少女、トリニティ=グラスフィールはにっこりと微笑む。
どこから走ってきたのか、決して運動が得意ではない彼女の息は少し乱れていた。そっと胸に手を添えて呼吸を落ち着かせて、トリニティはカズマのさっきまでの視線を追うように街並みへと首を巡らせる。
「綺麗ですよねぇ、ここから見えるイシャナは~」 -
ゆったりと、ゆったりと。
子守歌のような声色でトリニティが呟く。
カズマは返答らしいものを返さなかったが、彼女の感想に異はなかった。
イシャナは美しい。そして平和だった。
多少の小競り合いはあれど、危機らしい危機もなく、明日を当たり前に迎え、歴史を当たり前に重ねる、島の外の世界と同じように。
いつまでもここからの景色を眺めていられるように、世界の平和はいつまでも続くかのように思えていた。
「そういえばトリニティさん、僕になにか用があったんじゃ……?」
駆けてきた彼女は、自分を探しているようだったから。
カズマが問うと、トリニティはマシュマロのように白い指先を胸の前で合わせて目線を戻した。 -
「そうでしたぁ。私、カズマさんにお願いしたいことがあって。それで探していたんですぅ~」
「僕に……ですか?」
「はい。実は今度の、十聖の列聖式で使う法衣を作ってほしいと、お願いされまして~。そのための資料を集めるのを、手伝っていただけないでしょうかぁ~?」
ああ、なるほど。とカズマは納得した。
このイシャナ島は『魔道協会』という、どの国にも属さない組織が管理する都市だ。
『魔道協会』とは、この世界の裏舞台で脈々と受け継がれてきた『魔術』を管理し、その使い手を育て、またその技術でもって世界の礎を支え続ける人員の集まりである。 -
協会には最大十人の選ばれた魔術師たちが存在し、彼らが魔道協会の最高峰の意思決定機関となる。
それがすなわち『十聖』。
その特別な地位に、今度新たにひとり加わることになった。
十聖は現在八人。九人目の十聖として、列聖式に立つことになったのは、カズマやトリニティと同じくまだ学生の、少女だった。
「確かに……トリニティさんはこれ以上ない適任ですね」
「大役を仰せつかってしまいましたぁ」
嬉しそうにトリニティが笑う。
式典で使われる法衣は、特殊な錬金術で編む必要がある。 -
トリニティはこう見えて、魔道協会が管理する学園でも並ぶ者のない錬金術の使い手だ。彼女の手にかかれば、誰もが認める立派な法衣が出来上がるに違いない。
「それで、いかがでしょう? お手伝いしていただけますか~?」
「え、あ、いや、その。別にそれはいいんですけど……なんで僕に?」
大きな瞳に真摯な色を灯して、トリニティが見上げてくる。
その真っ直ぐな眼差しにたじろぎながら、カズマは戸惑いを返す。
地味で陰気で友達もいないカズマと違って、トリニティは人当たりもよく誰にでも優しい。喜んで手伝うような友人はいくらでもいるだろう。 -
カズマの疑問に、トリニティは少し悪戯っぽく肩を持ち上げてみせた。
「それは……実は、ですね」
――イシャナ、魔道協会内。
『大図書館』と呼ばれる建物は、魔道協会職員ですら許可証がなければ書の閲覧はもちろん、立ち入りも許されていない特別領域だった。
窓は極端に少なく、書を保管している部屋にはひとつもない。けれど室内は魔法の明かりに照らされていて、薄暗さや陰鬱さとは程遠い。
古めかしい木の本棚が整然と並ぶ大図書館の、中央部にある大きな机に錬金術関連の本を数冊積みながら、カズマは初めて踏み入った知識の宝庫をぐるりと見回した。もうこれで何度目になるだろう、繰り返した高揚のため息をまたも吐き出す。 -
「すごい、本当にすごい……! こんなに……ここにあるのが全部、魔道協会の保存書物だなんて」
蓄えられている知識は膨大だ。世界の歴史と可能性の全てと言ってもいい。
だがそれを閲覧するのは容易ではない。
カズマは何度か、ここの書物の閲覧を申請したことがあった。知りたいことがあったのだ。
だが許可が下りたことは一度もない。申請理由を明確に書けなかったせいだろう。
けれど十聖の法衣作成のためならば事情が違う。十聖の列聖式とは、それだけ魔道協会において重大な式典なのだ。
分厚い本を重たそうに机の上に置いて、トリニティがまた悪戯っぽい笑みを浮かべる。 -
「カズマさんが前に、ここの閲覧許可が下りないって言っていたのを思い出しまして~。どうせならご一緒にどうかなと、思ったんですぅ」
「覚えてたんですか? ……いや、わざわざありがとうございます。でもあの、関係ない本を勝手に読むのは、まずいのでは?」
「資料を探す中で、関係のない本を手に取ってしまうこともありますよ。だから……ちょっとだけ、です」
親指と人差し指で小さな隙間を作ってみせるトリニティの仕草に、カズマはへらっと力なく笑みを返した。
成績優秀、品行方正な優等生の彼女が時々見せるこういう一面には、毎度驚かされる。 -
「じゃあ、お言葉に甘えて……あとで少し。まずはトリニティさんのお手伝いからで」
どうせ個人的な調べものだ。カズマは椅子に座って、最初の本を開いた。
トリニティも正面の席で本を開き、目的の情報が乗っている箇所を探し始める。
しばらくはふたりのページをめくる音だけが聞こえていた。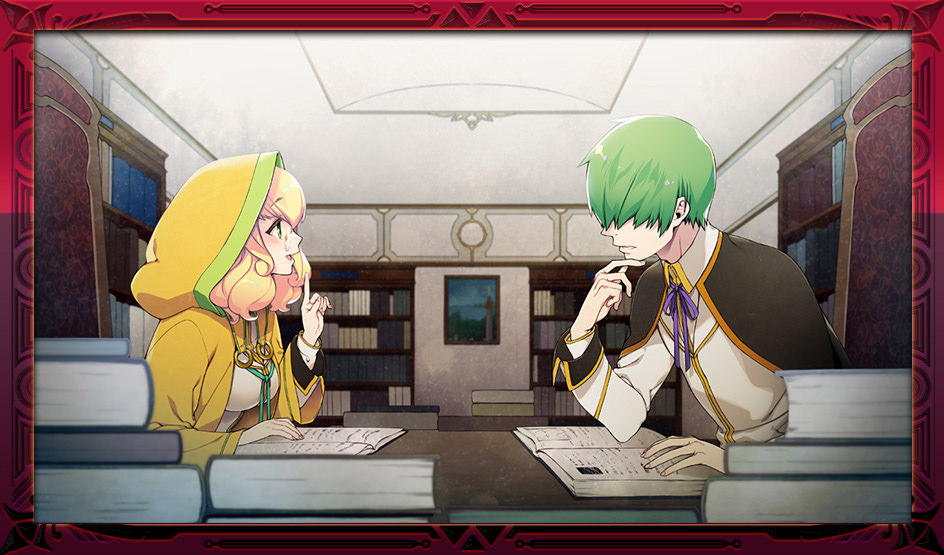
-
「……あの。十聖の法衣って、一から作り方を調べないといけないものなんですか?」
これまでも何度も使われてきたものなのだから、作り方くらい定型があるものだと思っていた。こうして錬金術の様々な技術を調べ出さねばならないとは、想像もしていなかったのだ。
カズマが窺うように見やると、トリニティもまたページをめくる手を止めてこちらへと視線を向け苦笑した。
「一応、基本の作り方はあるんですよ~。だけど今度の聖冠者は、今までとは違う形式の、特別な法衣をご所望なんですぅ。ですから、期待に添えるように細かいところもしっかり調べて、作りたいんですよぉ~。」 -
それを聞いて、今度はカズマが苦笑する番だった。
今度の聖冠者、十聖の九番目に名を連ねる少女は、魔術の才能と技術こそずば抜けて優秀だが、その分性格……というよりいっそ人格面に問題を抱えている、有名人だ。
その彼女の注文とあれば、さぞ複雑で難解なものなのだろう。
だがその彼女の注文だからこそ、トリニティは全力で応えようとしている。なにせ十聖の九番目となる少女は、トリニティの唯一無二の親友なのだから。
「……なるほど、そうだったんですね」
「あ。今『また厄介なことを言い出したんだろうな』って思いましたね?」 -
「へっ!? い、いや、その、僕は別になんというか……」
まったくその通りです。と、カズマは内心で大きく頷いていた。
「ふふふっ、実際そうなんですぅ。あの子ったら、次から次へと色んなことお願いするんですよぉ」
でも……と続けるトリニティの眼差しは、いつになく子供っぽく見えるほど嬉しそうで、楽しそうだ。
「大事な友達の、晴れ舞台ですから。あの子が想像している以上の、最高の法衣で式に出てほしいんですぅ~」
「大事な友達……ですか」
「どうかしましたかぁ?」
「いえ、僕にはちょっと、よくわからない感覚だなぁと思って。ほら僕、友達とかいないですから」 -
「まあ、そんな寂しいことおっしゃらないでください~。カズマさんだって、私の大事なお友達なんですから」
「あ……はあ。そうですか」
ほんの少し憤慨したようなトリニティの、それでも甘やかすような調子の言葉に、カズマは頬を引っ掻きながら曖昧な返事をするしかできなかった。
なんと言えばいいのかわからない。なにを感じるべきなのかわからない。
カズマのそんな感覚は、おそらく目の前の少女に伝わっているのだろう。トリニティは誠実とはお世辞にも言えないカズマの反応に、なにを咎めるでもなく、気分を害するでもなく、柔らかくくすりと笑った。
なんだかくすぐったい。カズマはぎこちなく笑みを返すと、手元の本に向き直る。 -
場の雰囲気を誤魔化すように適当にページをめくって、それから気付いた。
「この本……錬金術の本じゃなかったみたいです。なんだろう、歴史書、かな……」
言いながらカズマはページをめくる。
その先に現れた奇妙な文面に、吸い寄せられるように目が留まった。
詩だろうか。
つづられた古い言葉を、指でなぞり追いながら知らず知らずのうちに口に出していた。
「遠い東の地にて黒き災いが生まれ世界を覆う。その災厄を六人の英雄が打ち破るが、黒き災厄の躰からは混沌が生まれ落ち……」
――永遠なる『可能性という名の地獄』が始まる――。 -
たどたどしく読み上げていたカズマの言葉をさらうように、トリニティの声が先を続けた。詩のようなものは、まさしく彼女が言った通り綴られている。
「古いおとぎ話の一節ですよ~。小さいころ、魔術師だった両親からよく聞きましたぁ。確か……八つの頭を持つ黒い怪物が、世界中の人々を食べてしまう、だとか。そんな内容だったと思いますぅ。とっても怖くて、私それを聞いた夜はひとりで眠れませんでしたぁ~」
「はは……怪物の話を寝る前には聞きたくないですね」
昔を思い出して笑うトリニティにつられて、カズマも気の抜けた笑みを返す。
そのときだ。
「 見つけた 」
声が聞こえた。 -
カズマは弾かれたように振り返った。
声はすぐ側で、それこそ耳元くらい近くで聞こえた。
だが振り返った先には誰の姿もない。誰の気配もない。
「カズマさん?」
トリニティが心配そうに声をかける。
なんだったのだろう。幻聴だろうか。そうだろう。そうに違いない。
妙なことは、気のせいだということにしておくのが一番だ。カズマは緩慢に机に向き直り、小さくかぶりを振る。
「いえ、なんでもないです。すいません……」
きっと古めかしい、怪物の詩など読んだせいだろう。 -
はは、と軽く笑って、カズマは年代物の本を閉じると立ち上がった。
「この本、片付けてきますね。元あった場所がわからなくなると困……」
歩き出そうと踵を返したカズマの言葉は、最後まで続かなかった。
突然横から飛び込んできた凄まじい衝撃に力いっぱい吹っ飛ばされたからだ。
「ふぐおぉぉぉっ!」
日常生活ではまず発しないだろう悲鳴と呻きの中間の声を吐き出させられて、カズマは腰から折れて軽く飛び、冷たい床に叩きつけられる。
直後、何事かと起き上がろうとした頭を容赦のない力で踏みつけられた。 -
その感触で、カズマは自分の身になにがおきたのかを理解した。
「か、かかか、カズマさん!」
慌てて椅子を蹴り、駆け寄ってくるトリニティの足音が聞こえる。
それを遮るようにして、カズマの頭上から女の声が発せられた。周囲の人間をねじ伏せるような圧力のある、けれどまだ若い少女の声だ。
「駄目じゃない、トリニティ。『虫』は本を傷めるわよ」
見上げるまでもない。というより、見上げることは物理的に不可能だった。
床に倒れ伏すカズマの頭をヒールの尖った靴で踏みつけて、高圧的に告げたのはコノエ=マーキュリー。 -
誰もが振り向く抜群のプロポーションに、長い桃色の髪を流し、射抜くような鋭い眼光を持つこの少女こそ、十聖の九番目となる天才魔術師だ。
「こ、コノエ、いけませんよぉ。カズマさんが死んじゃいますぅ~!」
「このくらいで死ぬもんですか。害虫は丈夫さだけが取り柄でしょ」
不遜に言い放ちながらも、親友の言葉だからだろう、コノエはカズマの上から足をどける。
開放されたカズマは手近な椅子の背もたれにすがりながら、よろよろと起き上がった。
「コノエ=マーキュリーさん……いきなりなにを……」
「ふん!」
「おうぐぅぅ……」 -
 鈍い衝撃は、コノエの膝がえぐるようにカズマの腹部に叩き込まれたものだった。
鈍い衝撃は、コノエの膝がえぐるようにカズマの腹部に叩き込まれたものだった。
再び崩れ落ちそうになるカズマへ、先ほどトリニティへ向けられた声の主と同一人物とは思えない冷ややかな声が降ってくる。
「気安くその名前で呼ばないで。虫の分際で」
「す、すみま……せん」
飛び出しそうな内臓を飲み込んで、カズマは苦悶の中で呻くようにやっとそれだけ言葉を返した。 -
逆らおうなどとは微塵も思わない。この学園でコノエ=マーキュリーに盾突こうとする者など、よほどの命知らずか馬鹿だけだ。
コノエは長い髪を払い、形よくくびれた腰に手をあててトリニティへと顔を向ける。
「ねえトリニティ。今の作業は急ぎ? 一時間くらいでいいから、ちょっと手伝ってほしいんだけど」
「あらぁ、それは……どうしましょう~」
積み上げた本とカズマを見比べて、トリニティが薄桃色の頬に手を添える。
親友の視線を辿って、今初めて存在に気付いたかのように、コノエはうずくまるカズマを一瞥した。
「ああ、あと虫。教授が探してたわよ。頼んでたことがどうとかって」 -
「え? あ……あー……そうでした」
そういえば、とカズマは思い出す。確かに用事を頼まれていた。すっかり忘れていたが。
コノエはすぐにカズマから興味を失って、親友の細い肩をぽんと叩く。
「急ぎだったら、そっちが片付いてからでもいいわ。時間ができたらちょっと来て、工房で待ってるから」
「わかりましたぁ~。では、後ほど」
「じゃあね」
気取らない仕草で手を振って、コノエはハイヒールの音を鳴らしながら大図書館から足早に出ていった。
彼女が退出しきるのを待って、カズマはようやく身を完全に起こす。まだ腹部には鈍い衝撃の余波が残っていた。食後だったら、大図書館の床は無事ではすまなかったかもしれない。 -
「大丈夫ですかぁ?」
労わり覗き込むトリニティの優しい眼差しに、カズマは脂汗の気配を感じながらも苦笑を作った。
「十聖の選考基準に、慈愛の心の意義を説きたい気分ではあります……」
「うう……ああ見えて、妹思いで優しいところもあるんですよぉ」
「はは……またまた、冗談を」
トリニティが冗談を言うような人でないとわかっていたが、カズマはわざとおどけた調子で言った。あまり彼女に心配もさせたくなかった。
「そうだ、僕……コノエさんが言ってたように、教授に用事を頼まれてまして。すみません、手伝うと言ったのに」 -
「でしたら、また後でご一緒していただけませんかぁ? 私もちょうど、コノエに呼び出されたことですからぁ~」
「いいんですか……?」
まだ大図書館の本をほとんど読んでいない。トリニティの申し出は願ったりかなったりだ。
トリニティが目を細めて、甘く微笑む。
「もちろんですぅ~」
平和な世界、のどかな島、少しだけ騒がしい学園、周囲になじめない陰気な人間にも優しく気を使ってくれるクラスメイト。それがカズマの、今ある日常だった。 -
トリニティとは大図書館の前で別れて、カズマはひとり学園の正門へ向かって歩いていた。
長い前髪に隠れた金色の瞳はガラス玉のようで感情の色に乏しく、閉ざされた口元に表情らしいものはない。
さっきまでは、それなりに人間らしく戸惑いや笑みなんかを形作っていたのに。あらゆる感覚が鈍った、人形のような無表情で、淡々と足を進める。
教授からカズマが頼まれたのは、転入生の案内だ。
この時期に珍しいことだが、聞いた話では書類の不備があって色々な手続きが少しずつ遅れてしまったことが原因らしい。 -
学園の正門は広大だ。
正門中央にあるエントランスの壁には、魔法陣を模した大きな時計が設置されていた。
それを物珍しそうに眺める学生服姿を見つけて、カズマは小走りに近寄る。そのころにはもう、彼の口元には『いつものように』覇気のない笑みが作られていた。
「すみません、お待たせしてしまって」
カズマの声に、時計の前の人物が振り返る。
大きな時計の針が、静かに動いた瞬間だった。
1/29